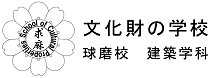九州旅客鉄道肥薩線大畑駅舎
建物データ
| 名 称 | 九州旅客鉄道肥薩線縁大畑駅舎 明治42年(1909)開業 木造平屋建、、切妻造、桟瓦葺、平入、三方庇付、南向 |
|---|---|
| 指定年月日 | 駅舎は文化財の指定はありませんが、2007年(平成19年)11月30日に大畑駅周辺の鉄道施設遺産群、大畑駅石造りの給水塔・朝顔型噴水が「近代化産業遺産群」に認定遺産されています。 |
| 所在地 | 人吉市大野町 |
| 修理記録 | 観光列車「いさぶろう・しんぺい」のリニューアルにあわせて窓枠を木造に戻すなど、開業当初の雰囲気を再現する改装が行われた。 |
| 保存修理工事報告書 |
大畑駅舎正面

大畑駅の開業は明治42年で、蒸気機関車が水を補給するために作られた駅のため、当時から駅周辺には人家はありません。大畑駅はループ線上にある3段スイッチバックと、急な上り坂を緩やかにするための線路が直径600メートルのループを備えており、日本ではここにしかない構造の線路です。
大畑駅舎線路側

昭和61年11月1日に電子閉塞装置導入により無人駅となりました。
大畑駅舎改札口

駅舎から構内踏切を渡って、島式ホーム1面2線に行くことができます。
大畑駅舎内部

自分の名刺を貼ると出世するという話から、駅舎には大量の名刺が貼られていましたが、現在、貼られていた名刺は剥がして保管され、建物内部の様子が分かるように、名刺を貼る場所が決められています。
給水塔

明治42年開業当時、人吉駅から矢岳駅へと続く道は勾配がきつく、蒸気機関車は途中で給水をしなくてはなりませんでした。そこで、ループ線を用いて傾斜を緩やかにしながら、矢岳駅へと登って行く途中の平坦な場所にスイッチバックを設け、給水塔のある駅を建設されました。
朝顔型噴水